許認可関係
1. 探偵業許可
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
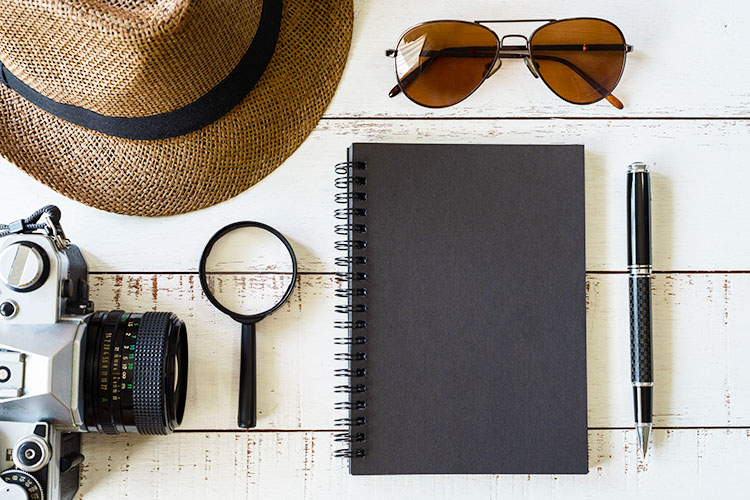
2. 古物商許可
古物商許可とは、古物営業法に規定される古物を売買し古物商として営業を行うために、営業所を管轄する都道府県公安委員会から得る許可のことで、古物商許可は盗品の売買などの犯罪防止する目的で設けられたものです。古物商許可証の交付の実際の窓口になってやり取りをするのは管轄の警察署となります。
古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。あくまで中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

具体的には以下のケースが対象となります。
- 古物を買い取り売る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
上記に該当する取引は基本的に古物商許可が必要となりますが、例外もあります。
3. 簡易宿所営業許可
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、
旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」については、ここ数年、
インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者と
をマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、日本でも急速に普及
しています。
こうした状況を踏まえ、平成30年6月15日より、新たな民泊サービスの
枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行
えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
旅館業法に基づいて民泊サービスを実施するためには
- 許可が必要です。
(旅館業法施行令第1条第2項(簡易宿所営業における構造設備基準) - 許可取得までの流れ(旅館業法)
事前相談 ⇒ 許可申請 ⇒ 施設検査 ⇒ 許可 ⇒ 営業 - 営業を開始してから必要なこと
営業に当たっては、寝具の交換、浴室等々の清掃などの衛生管理を適切に行う義務や宿泊者名簿を備え付けることが義務づけられています。
詳しく、知りたい方は、お問い合わせからご相談をお願いします。

4. 法人設立・飲食店許可等
法人設立
(1)営利法人
・株式会社(特例有限会社を含む) ・合同会社 ・合資会社 ・合名会社
(2)非営利法人
・一般社団法人 ・公益社団法人 ・一般財団法人 ・公益財団法人 ・宗教法人
・学校法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人)
無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリヘル営業は専門で届出の書類を作成提出いたします。開業する際には、営業開始前に警察へ許可申請届出が必要となります。
その他店舗型性風俗特殊営業開始届出等は、まず御相談をお願いします。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、一般的な飲食店を開業するうえで必要です。保健所から飲食店営業許可証を取得することで、店舗で調理した料理や、午前0時までの酒類の提供が可能になります。別の場所に複数店舗を開業する場合は、それぞれ店舗ごとの申請が必要です。なお午前0~6時に営業する場合、また居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要があります。

交通事故調査関係
- 被害者請求
加害者の自賠責保険会社に対して被害者の損害賠償を請求します。 - 後遺障害等級認定申請
被害者の後遺障害等級を認定する手続きを行います。 - 事故現場調査(車両の破損状況含む)
事故現場の見通しや交通量、目撃者等の調査を行い、事故の状況や事故原因を明らかにします。

行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書作成等の手続を行います。また、被害者に代わり、自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
過失割合などでもめている場合、弁護士とも連携できますので、お気軽に御相談下さい。
遺産・相続関係
- 戸籍謄本等の取得代理申請
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の確定調査
- 相続関係図の作成
- 相続財産調査及び目録の作成
- 遺言書作成に伴う相談
- 葬祭費等代理申請
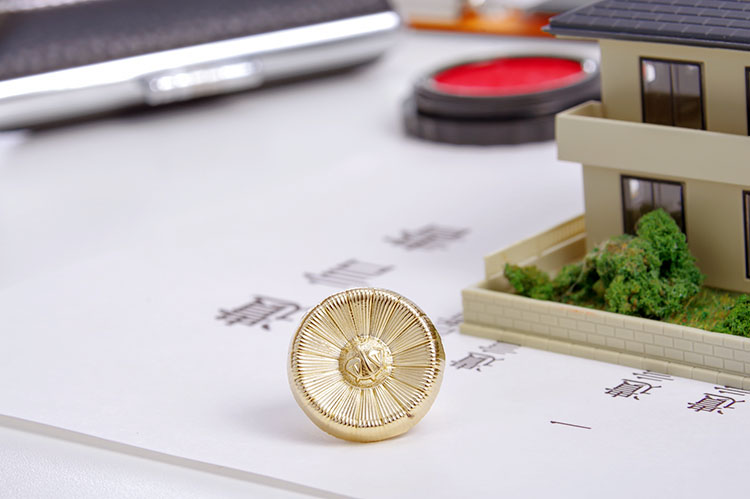
遺産相続関係は、多種多様にわたり、同じ扱いの物はありません。まずはお問い合わせから御相談からお願いします。
遺言書には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言については、自宅等に保管も可能ですが、法務局で行っている遺言書保管制度を御利用することをおすすめします。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
離婚協議及び公正証書原案作成関係
日本全国の離婚件数の約90パーセントは協議離婚と言われています。残り10パーセントは、調停、裁判等々ということであり、ほとんどの方は、揉めることを望んでいないということになります。
弁護士であれば、協議離婚から裁判まで対応できるので、幅広く対応できるのですが、報酬料はかなり高額となり、中には財産分与等々でもらえる金額よりも弁護士報酬が高いということもあり得ることで、最後の砦として行政書士にたどり着いて、協議を進めていけるようになったと感謝の言葉もいただいております。
行政書士は、弁護士と違い、交渉や示談はできませんが、離婚協議を進めていく過程で適宜適格にアドバイスを行い、離婚協議書を作成するということになりますので、報酬額は高額になることはありません。離婚協議書を作成されてからは、それを公正証書にしたいという方も一定数おりますが、案件を吟味すると、確かに公正証書にした方がいい場合の方が多いです。
又協議離婚は同じものは存在しません。それぞれ微妙に違いがあり、話合いがスムーズにいかない、協議に全く応じない、話の意図を理解してくれないなど、協議が難航することもあります。正確な文章で作成しないと第三者に伝わらないという複雑な場合がありますので、まずは、内容証明郵便を使い通知を行う。しかし話し合いに応じないない場合は受取拒否などの対応をされます。受取拒否やその他受取がされない場合は特定記録郵便を送付するという手法もあります。まずは当事務所にお問い合わせをしていただき、打ち合わせ、対応策を綿密に行いたいと思います。
- 離婚協議書の作成
- 公正証書原案作成と手続きの代行
- アドバイスを含めたフォロー
- 内容証明の原案作成(通知代理人として作成します。)

その他、お手伝いできる業務もありますのでお気軽にご相談をお願いします。
お気軽に相談 確かな手続き あなたの街の行政書士 行政書士は、街の身近な法律家です。