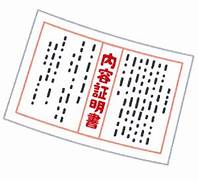相続手続前にやっておきたい手続きの流れと期限
1 死亡診断書の受け取り

家族が亡くなったら、当日あるいは翌日に医師から死亡診断書の交付を受け、死亡届を市区町村役場へ提出します。診療中の病気以外の理由で亡くなった場合や、不慮の事故などにより亡くなった場合は、警察を通じて、医師(監察医)に死体検案書を交付してもらいます。
2 死亡届と火葬許可申請書の提出
死亡届は死亡証明書と一体になっており、右半分が死亡証明書、左半分が死亡届です。死亡届に必要事項を記入したら、死後7日以内に火葬許可申請書と一緒に故人の死亡地あるいは本籍地などの市区町村役場に提出します。
(死亡診断書等は各種手続きに必要になりますので提出前に多めに10枚ほどコピーしておくとよいです。葬儀社が提出の代行をしてくれる場合もコピーを多めにとっておいてもらいましょう。)
3 葬儀に関すること
最近では家族葬や直葬も増えていますが、一般的には葬儀社に依頼して、お通夜や葬式などの法要をおこない、お墓や仏壇を用意します。葬儀費用は相続税を申告する際に相続財産から控除できるものがあります。葬祭費は助成金の対象です。領収書は無くさないように!
4 年金受給停止の手続き
故人が年金受給者であれば、すみやかに年金の受給停止の手続きをします。過剰に受け取った年金は返還しなければなりません。年金事務所または街角の年金相談センターに年金受給権者死亡届を提出するのですが、厚生年金の受給停止手続きは死亡後10日以内、国民年金の受給停止手続きは死亡後14日以内におこなわなければいけません。
5 健康保険の資格喪失の手続き
健康保険の被保険者が亡くなった場合は、資格喪失の手続きをして、健康保険証を返却します。
各健康保険によって手続きが異なりますので、健康保険の種類に応じて手続きしましょう。
国民健康保険と後期高齢者医療保険の場合は、死後14日以内に故人の住所地の市区町村役場窓口に、国民健康保険被保険者資格喪失届や後期高齢者医療被保険者資格喪失届を提出します。
健康保険の場合は、死後5日以内に勤務先の会社や協会けんぽ、健康保険組合に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出します。
6 介護保険の資格喪失の手続き
故人が65歳以上または40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合は、死後14日以内に故人の住所地の市区町村役場窓口で介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届の提出を併せておこなう必要があります。
7 世帯主変更届の提出
世帯主が亡くなったら、世帯主変更届(住民異動届)を市区町村役場へ提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。この手続きは通常、死亡届と併せておこなうことになりますが、期限としては死後14日以内になります。
8 公共料金や各種サービス等の名義変更・解約など
故人名義のさまざま契約に関して変更・解約手続きをおこないましょう。これらの手続きには期限はありませんが、有料のものはすみやかに解約手続きをおこない余分な出費を抑えましょう。
9 金融機関への連絡
金融機関に口座名義人の死亡を連絡して、公共料金・家賃等の引落しがストップすると困るな どの事情がなければ口座を凍結してもらいます。他の相続人が勝手に出金してしまうことを防ぐためですが、葬儀費用や当面の生活費に困らないように、事前に準備しておく必要があります。
事前に資金を用意していなかった場合には、遺産分割前における預貯金の払戻し制度(上限1 50万円)を利用します。
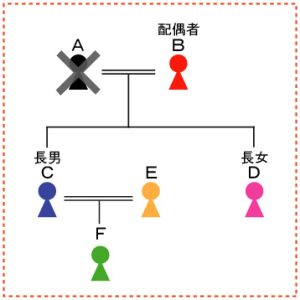
被相続人が亡くなってから相続手続きに至るまでの準備は結構やることが多く、チェック表などを作成しておいて終わったものにはチェックを入れておくというような工夫も必要かと思われます。